「亭主関白」とは、
- 家庭内における夫の強い権威を示す言葉
を意味する日本の表現です。
この表現は、夫が家庭の主導権を握り、妻に対して支配的な立場を取る様子を示しています。近年では、男女平等が進む中で、その意味合いも変化しつつあります。
この記事では、「亭主関白」の意味、対義語、類義語、使用した例文、関連する文化背景まで詳しく深掘りして紹介します。
この記事で分かること
- 『亭主関白』の意味、対義語・類義語・例文・文化的背景をまとめてご紹介します。
目次
「亭主関白」ってどういう意味?
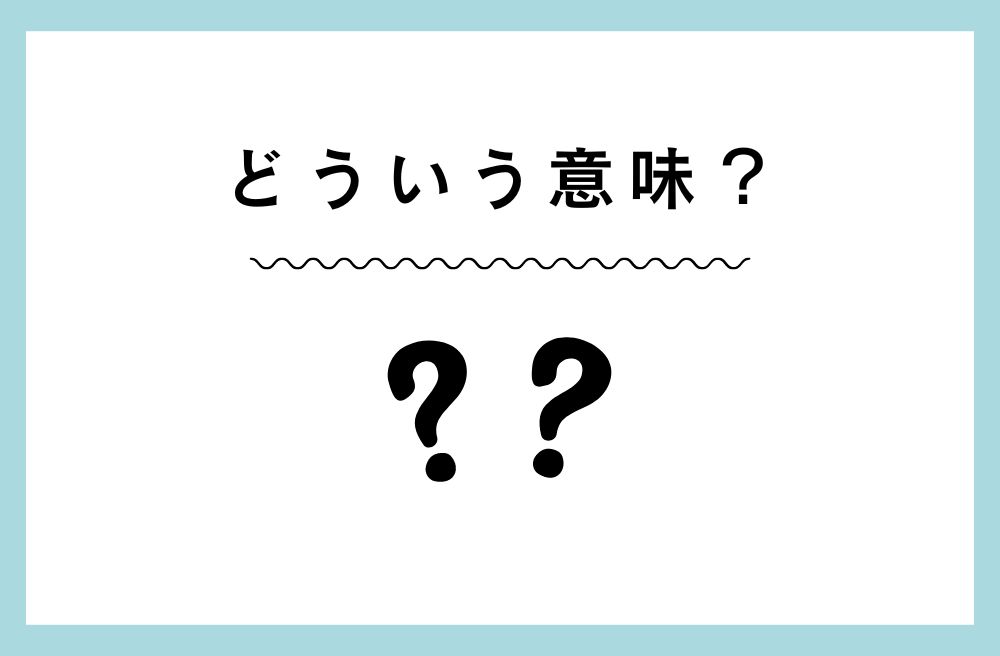
「亭主関白」とは、家庭内で夫が優位に立ち、妻がその意向に従う形を指す言葉です。
この表現は、特に日本の伝統的な家族構造において顕著でしたが、現代ではその意味や受け止め方が変化しています。
「亭主関白」の反対の意味をもつ言葉は?
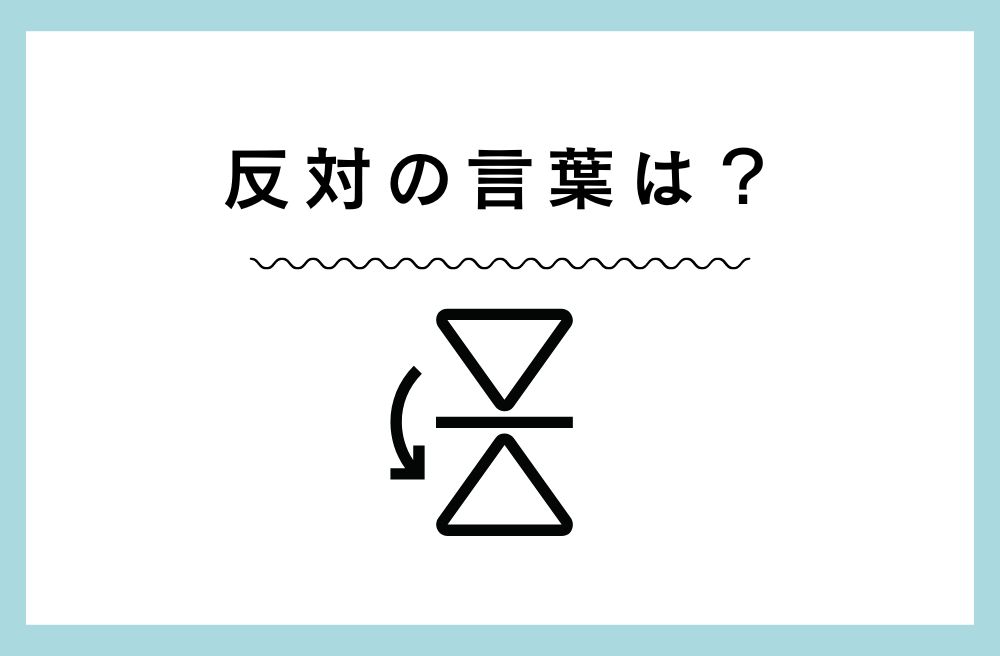
- 共働き – 夫婦双方が働き、家庭内の役割を分担すること。
- 男女平等 – 性別による役割の違いがないこと。
- 対等な関係 – 夫婦が対等に意見を出し合い、共に決定すること。
- パートナーシップ – 相互に支え合う関係。
- 協力的な家庭 – 家庭内での協力が重視されること。
「亭主関白」と似た意味をもつ言葉は?
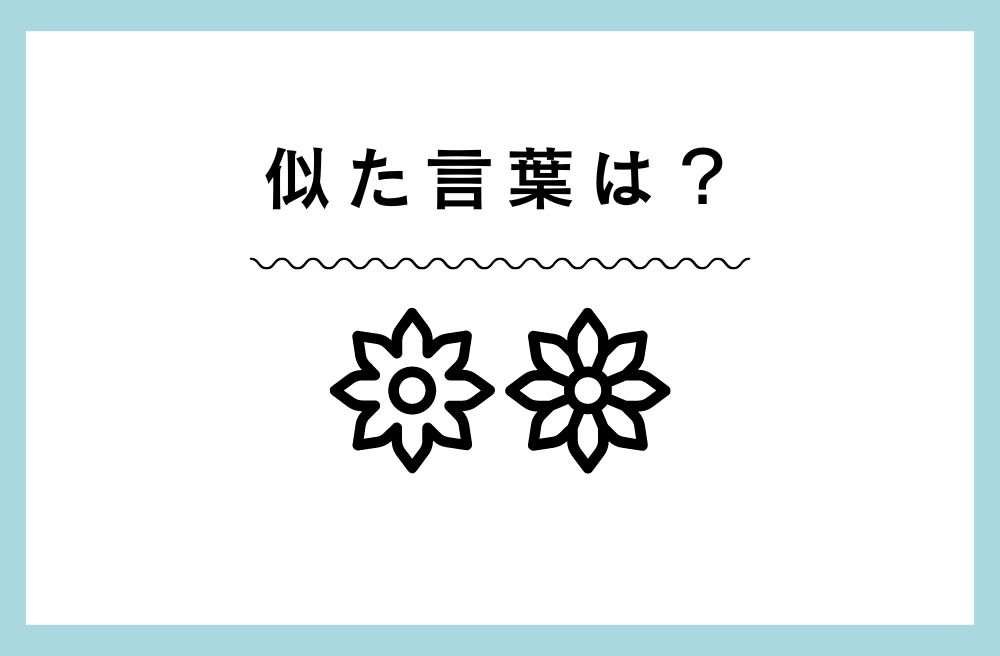
- 夫権主義 – 夫が家庭内での権利を持つ考え方。
- 伝統的な家族観 – 家庭内の役割分担が固定されている考え方。
- 男性優位 – 性別による優劣を重視する観点。
- 家父長制 – 男性が家族の長として支配する制度。
- 権威主義的家庭 – 家庭内での権威が重視される家庭。
「亭主関白」を使った例文は?
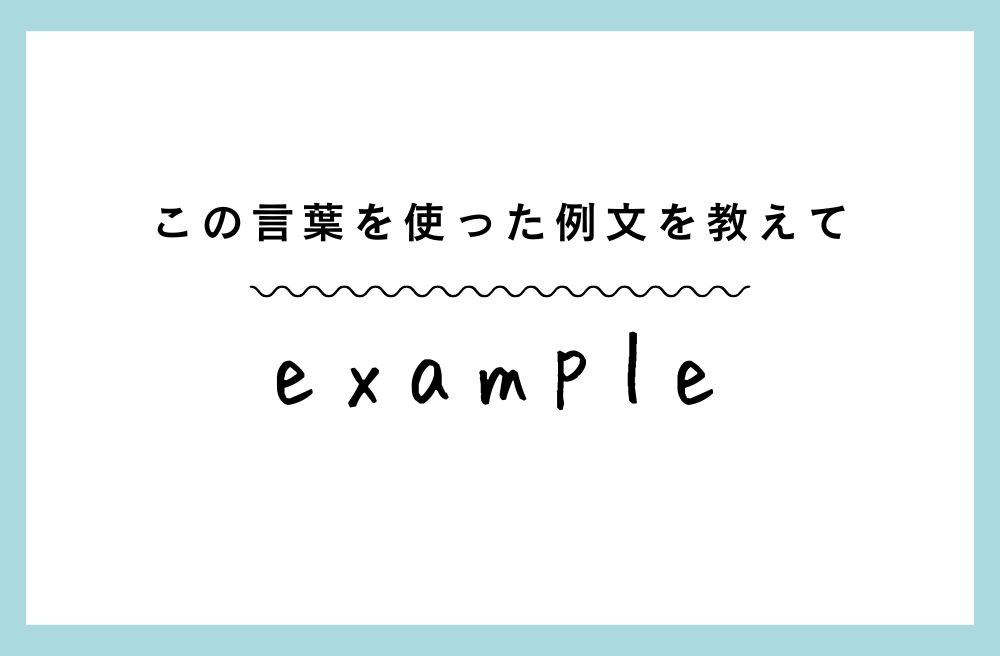
- 彼は亭主関白で、家のことは全て自分が決めると言っている。
- 最近の若い夫婦は亭主関白の考え方を嫌う傾向がある。
- 亭主関白の家庭では、妻が意見を言いにくい場合が多い。
- 彼女は亭主関白の夫に対して不満を持っている。
- 亭主関白の考え方は、時代遅れだと感じる人も多い。
「亭主関白」の文化的背景
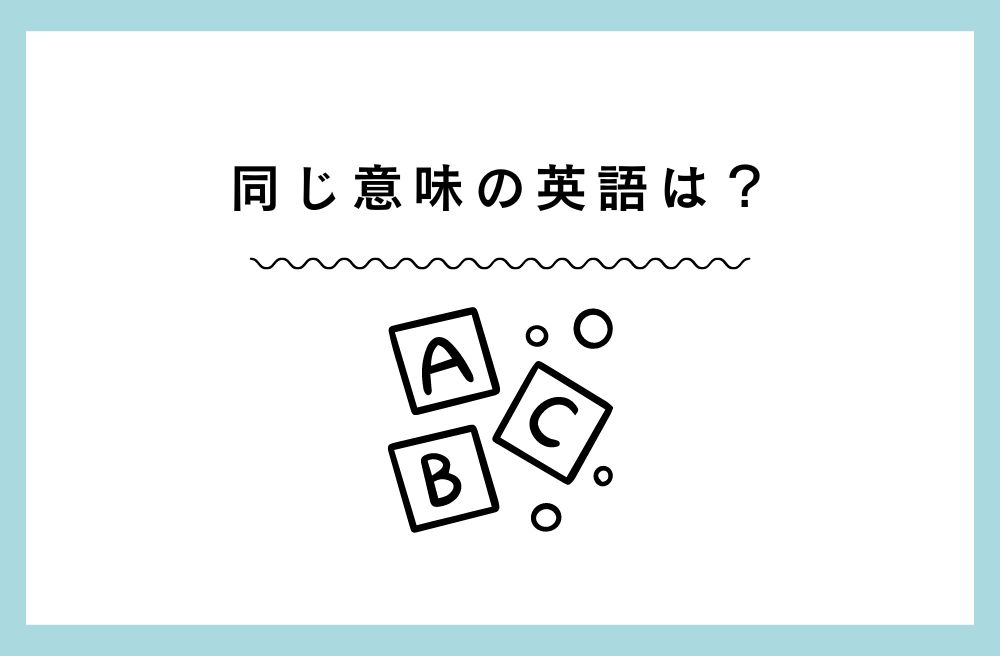
「亭主関白」は、日本の伝統的な家族構造において、夫が家の主としての役割を果たすことを強調する表現です。この考え方は、長い歴史を持ち、農業社会や戦前の時代には特に顕著でした。現在では、男女平等の考え方が浸透し、家庭内の役割分担も多様化していますが、依然としてこの言葉は存在し、時には批判の対象となります。
最後に
この記事では、『亭主関白』の意味、対義語・類義語・例文・文化的背景をまとめてご紹介しました。
「亭主関白」は、伝統的な家庭観と現代の価値観がぶつかるテーマであり、男女平等の意識が高まる中で見直されるべき言葉でもあります。この教訓を参考に、家庭内での役割分担についての考え方を見直してみることが大切です。
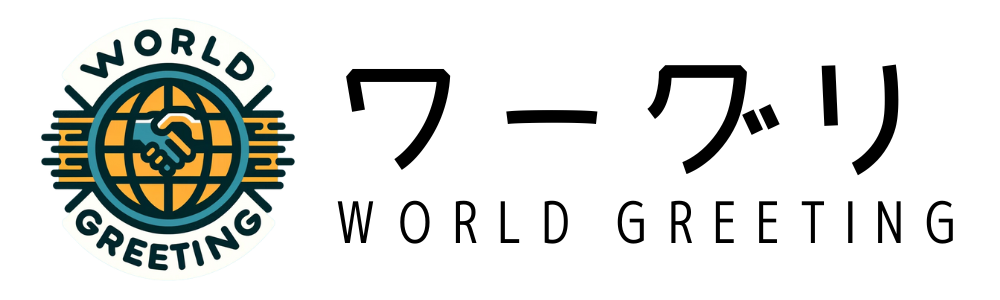
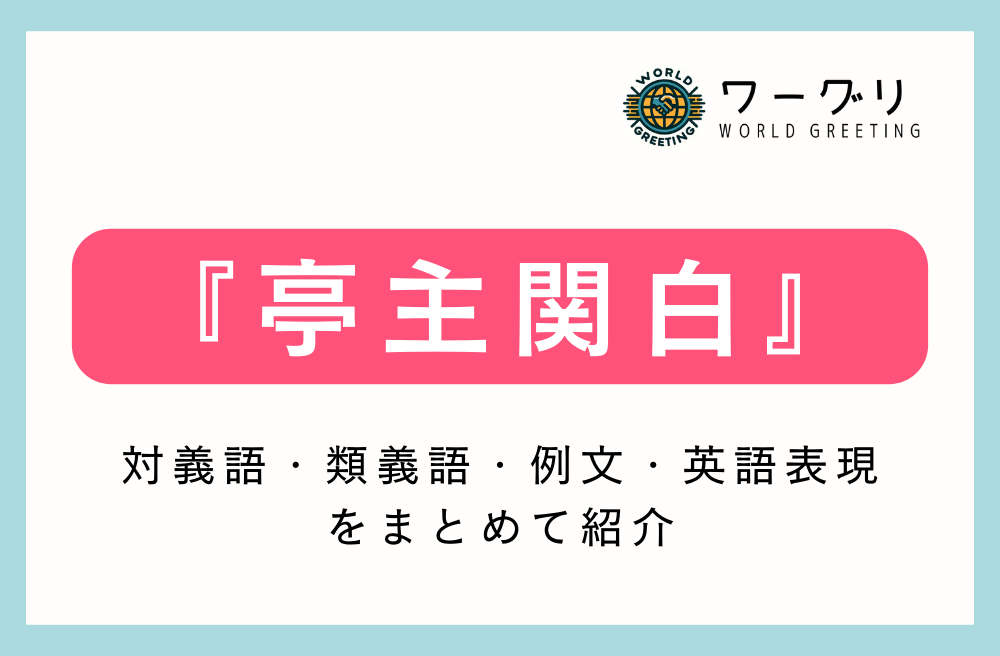









コメント