「ことわざ」は、時を超えて受け継がれる先人からの贈り物です。
私たちの日常生活に深く根ざし、世代を超えて知恵や教訓を伝えるために用いられてきました。
この記事では、広く使われている140以上のことわざとその意味を一挙に紹介します。
- よく使われる「ことわざ」とその意味を一覧で詳しく紹介しています。
ことわざ一覧・140選
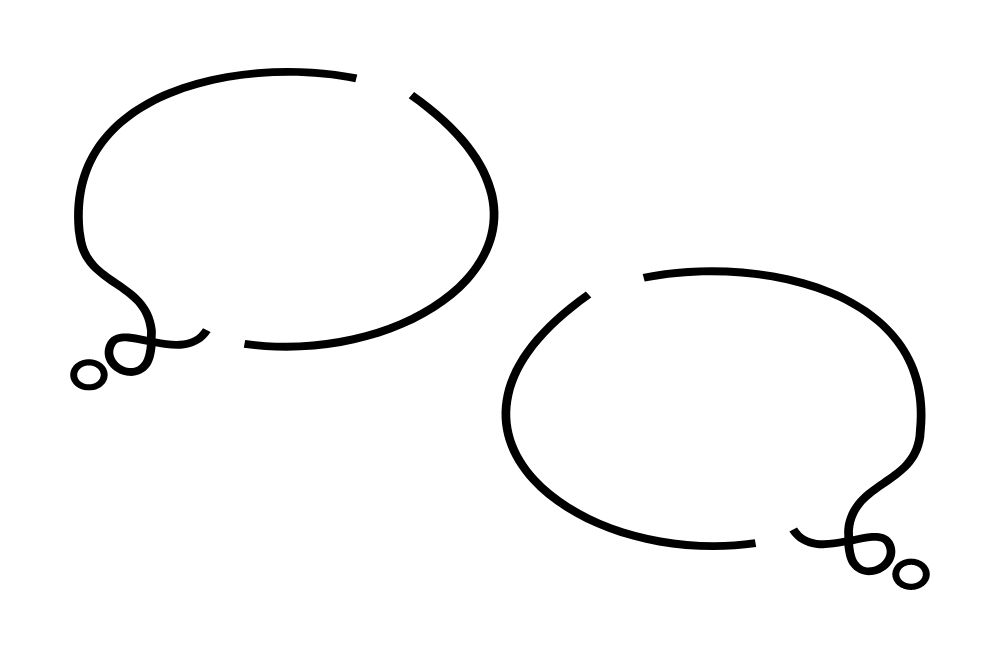
いずれ菖蒲か杜若
どちらも美しい花である菖蒲(しょうぶ)と杜若(かきつばた)を比べることから、似たような良いものや優れた人物を比べることの難しさを表しています。
悪事千里を走る
悪いニュースや噂はすぐに遠くまで広まるという意味です。
案ずるより産むが易し
心配している時よりも、実際に行動に移した方が簡単であることが多いという意味です。
井の中の蛙大海を知らず
狭い範囲の中でしか経験や知識がない人は、広い世界や大きな可能性を知らないという意味です。
井戸を掘って水を飲む
「水を飲むときには,その井戸を掘ってくれた人のことを忘れないように」という意味です。
一を知って十を知る
少しの情報から多くのことを推測する能力、または一部を見て全体を理解することの大切さを表しています。
一を聞いて十を知る
「一を知って十を知る」と同様に、わずかな手がかりから多くのことを理解する洞察力や推理力を称える言葉です。
一期一会
一生に一度の出会いを大切にすべきだという意味で、茶道などで用いられることが多い言葉です。
一刻千金
非常に貴重な時間のことを言い、一瞬一瞬を大切にすべきだという意味があります。
一事が万事
一つのことが全てを表しているという意味で、小さいことからその人の性格や能力が推測できるということを示しています。
一寸の虫にも五分の魂
小さな生き物にも命があるということを教える言葉です。全ての生命には価値があるという意味を持っています。
一寸先は闇
未来は予測不可能であるという意味です。どんなに計画しても、次に何が起こるかは分からないということを表しています。
一石を投じて百鳥を驚かす
一つの行動で多くの効果を上げることを意味します。少ない努力で大きな成果を得ることの比喩です。
一石二鳥
一つの行動で二つの利益を得ることを意味します。効率的な行動を称える言葉です。
一難去ってまた一難
一つの問題が解決しても、また新たな問題が発生するという意味です。
一日の長
時間の経過によって生じる利点や優位性を指します。また、わずかな差が大きな違いを生むことを示しています。
芋の煮えたも知らぬ
物事に鈍感であること、または周りの状況に無頓着であることを表す言葉です。
鰯の頭も信心から
どんなにつまらないものでも、それを大切にする心があれば価値があるという意味です。
雨後の筍
事が次々と起こる様子や、物事が急速に発展する様子を表す言葉です。
雨降って地固まる
困難やトラブルを経験することで、人や組織がより強固になることを意味します。
瓜の蔓に茄子はならぬ
本質的な性質は変わらないという意味です。親から生まれた子は、その親に似ているということも表しています。
猿も木から落ちる
どんなに得意なことでも、失敗することがあるという意味です。
縁の下の力持ち
目立たないが、実は大きな力を発揮している人のことを言います。
縁は異なもの味なもの
人と人との縁は不思議なもので、思いがけない形でつながることがあるという意味です。
遠くの親戚より近くの他人
地理的に遠い親戚よりも、身近にいる他人の方が頼りになることがあるという意味です。
恩を売って仇を買う
良いことをしたつもりが、かえって恨まれる結果になることを意味します。
果報は寝て待て
良いことが起こるのを焦らずに待つべきだという意味です。
河童の川流れ
どんなに上手な人でも、失敗することがあるという意味です。
火のない所に煙は立たぬ
うわさが立つには何らかの原因があるという意味です。
花は桜木人は武士
物事や人にはそれぞれの代表があるという意味です。美しい花は桜、立派な人は武士がそれにあたるとされています。
花より団子
実用性や実利を美しさよりも重視することのたとえです。
過ぎたるは及ばざるが如し
何事も度を過ぎると、不足しているのと同じくらい良くない結果を招くという意味です
蚊帳の外
重要なことから除外されている、または関与していない状況を表します。
我が身を振り返れば千の秋
長い時間を感慨深く振り返ることを意味します。
開いた口に餅
思いがけない幸運が舞い込むことを意味します。
開口一番
何かを話し始めるとすぐに、最初に言うことを意味します。
蛙の子は蛙
子は親に似るという意味です。
楽あれば苦あり
楽しいことがあれば、それに伴う苦労もあるという意味です。
鬼に金棒
すでに強いものがさらに強くなることを意味します。
鬼に金棒、猿に小判
それぞれのものにとって最適なものが与えられた状態を意味します。鬼にはさらに強くなる金棒、猿には価値を理解できない小判という、場合によってはその価値を生かせないものをもたらすことの例え。
鬼の居ぬ間に正月
厳しい人がいない時には自由に楽しめるという意味です。
鬼の居ぬ間に洗濯
「鬼の居ぬ間に正月」と同様に、厳しい目がないときに好きなことをするという意味です。
鬼の目にも涙
どんなに冷酷な人でも情のあるときがあるという意味です。
亀の甲より年の功
長年の経験は見た目以上の価値があるという意味です。
亀の歩み
非常に遅い進行を意味しますが、着実に目標に向かって進むことの価値を示していることもあります。
泣きっ面に蜂
すでに悪い状況にあるのに、さらに悪いことが起こるという意味です。
泣く子と地頭には勝てぬ
泣いている子供や地元の有力者には対抗できないという意味です。
魚心あれば水心
相手が好意を持っていれば、こちらもそれに応えるという意味です。
蛍雪の功
苦労して勉強した成果が後に大きく花開くことを意味します。
鶏を割くに焉んずる剣
過剰な力は必要ない場面での使用を戒める言葉です。小さな問題に過剰な手段を使うべきではないという意味があります。
鶏口となるも牛後となるなかれ
小さな集団のリーダーである方が、大きな集団の末端の一員であるよりも良いという意味です。
月とすっぽん
比べ物にならないほどの差があることを意味します。
犬が西向きゃ尾は東
物事は相反する要素を含んでいることの例えです。
犬も歩けば棒に当たる
行動を起こせば、良くも悪くも何らかの結果が出るという意味です。
犬猿の仲
仲が非常に悪いことを意味します。
見ぬが花
実際に見るよりも想像した方が美しいという意味です。
言わぬが花
言葉に出さない方が良いこともあるという意味です。
枯れ木も山のにぎわい
価値がなさそうなものでも、それがあることで全体の雰囲気が良くなるという意味です。
虎穴に入らずんば虎子を得ず
大きなリスクを冒さずして大きな成果は得られないという意味です。
五十歩百歩
大差ないことを示します。少しの違いを争っても意味がないということを言います。
後の祭り
時機を逸してしまった状態を表します。事が終わった後では何をしても遅いという意味です。
後悔先に立たず
事を成し遂げた後に後悔しても、時既に遅しということです。
口は災いの元
不用意な発言が原因でトラブルになることを警告します。
弘法にも筆の誤り
どんなに上手な人でもミスをすることがあるという意味です。
塞翁が馬
禍福は互いに転換しやすいということを表します。良いことが悪く、悪いことが良く転じる可能性があるという教訓です。
三日坊主
続かないこと、すぐにやめてしまう人のことを指します。
枝葉末節を断つ
重要でない細かい部分を取り除くという意味です。
七転び八起き
何度失敗しても諦めずに立ち上がることの大切さを表します。
七転八倒
激しい苦痛や悩みで苦しむ様子を表します。
捨てる神あれば拾う神あり
不幸や困難があっても、それを救ってくれる存在や機会があるという意味です。
釈迦に説法
知識がある人にその知識を教える無意味さを表します。
弱肉強食
強い者が弱い者を支配する自然の法則や社会の実情を表します。
手綱を緩めて馬を制す
柔軟な対応で相手をうまくコントロールすることを意味します。
朱に交われば赤くなる
環境や付き合う人によって、人の性質や行動が変わることを示します。
十人十色
人にはそれぞれ異なる意見や好みがあるという意味です。
出る杭は打たれる
突出した存在は批判や攻撃の対象になりやすいという意味です。
初心忘るべからず
始めた当初の心持ちや意気込みを忘れてはならないという教えです。
焼け石に水
効果がほとんどない無意味な努力を表します。
笑う門には福来る
明るく楽しい家庭には自然と幸運が訪れるという意味です。
森羅万象
宇宙に存在するあらゆる事象や物体を指します。自然界の全てを包括するという意味があります。
身から出た錆
自分のしたことが原因で問題が起きること。自業自得の意味です。
身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ
大きなリスクを冒すことで、逆境を乗り越えることができるという意味です。
身を切られるような心痛 / 身を切るような心痛
非常に強い精神的苦痛を感じることを表します。
人の噂も七十五日
人の噂も時間が経てば忘れられるという意味です。
人の振り見て我が振り直せ
他人の行動を見て、自分の行いを反省し改めるべきだという意味です。
人の褌で相撲を取る
他人の力を借りて自分の目的を達成しようとすることを意味します。
塵も積もれば山となる
小さなことでも積み重ねれば大きな結果になるという意味です。
>>>『塵も塵も積もれば山となる』を詳しく確認
>>>『塵も積もれば山となる』を世界各国の言葉でいうと?
雀百まで踊り忘れず
年を取っても一度身につけた技術や習慣は忘れないという意味です。
石の上にも三年
辛抱強く努力し続ければ、いずれ良い結果が得られるという意味です。
石橋を叩いて渡る
用心深く慎重に物事を進めることを意味します。
栴檀は双葉より芳し
価値のあるものは初めからその兆候を見せるという意味です。
船に刻むべからず
過去に執着して未来を損ねるべきではないという警告です。
船頭多くして船山に登る
指揮命令者が多すぎると、物事がうまく進まなくなるという意味です。
前門の虎、後門の狼
あらゆる方向から危険が迫っている状況を表します。
袖振り合うも多生の縁
一見すると偶然の出会いでも、何世代にもわたる因縁があるという意味です。
棚から牡丹餅
思いがけない幸運が舞い込むことを意味します。
暖簾に腕押し
効果のない行為をすることを意味します。
知らぬが仏
知らないことには悩まされないという意味です。知らないことが幸せである場合があるという教えです。
地獄の沙汰も金次第
お金があれば、どんな困難な問題も解決できるという意味です。
朝起きは三文の得
早起きすることによる利点や得があるという意味です。
鶴の一声
権威ある人の決定的な一言によって、物事が決まることを意味します。
転ばぬ先の杖
事前の準備や予防策が重要であるという意味です。
兎に角
とにかく、何としてもという意味で使われます。問題解決のためには手段を選ばない様子を表します。
渡る世間に鬼はなし
この世は思いやりのある人ばかりで、本当の意味での悪人はいないという楽観的な見方を示します。
当たって砕けろ
思い切って挑戦し、たとえ失敗しても悔いは残らないという意味です。
鳶が鷹を生む
平凡な親から非凡な子が生まれることを意味します。
二階から目薬
方法が非効率的で、効果が期待できないことを意味します。
二兎を追う者は一兎をも得ず
二つの目標を同時に追求すると、どちらも達成できないという意味です。
猫に小判
価値のわからない人に貴重なものを与えても無駄であるという意味です。
猫の手も借りたい
忙しい時にはどんな助けでも欲しいという意味です。
能ある鷹は爪を隠す
本当に能力のある人はそれをあからさまに見せびらかさないという意味です。
馬の耳に念仏
どんなに良いことを言っても、聞く耳を持たない人には効果がないという意味です。
馬子にも衣裳
外見を飾ることで印象が良くなるという意味です。
馬耳東風
人の忠告や批判を聞き流すことを意味します。
飛んで火に入る夏の虫
自ら危険な行動をとって災いを招くことを意味します。
瓢箪から駒
思いがけない幸運や意外な結果を表します。
腐っても鯛
価値のあるものは、状態が悪くなっても価値があるという意味です。
負けず嫌いの石橋を叩いても渡らぬ
極端に慎重すぎる性格の人は、たとえ安全であっても挑戦を避けることを意味します。このことわざは一般的に知られているものではなく、特定の状況や解釈を示唆している可能性があります。
負けるが勝ち
直接的には負けたように見えても、長期的な観点や道徳的な観点から見ればそれが最終的には利益につながるという意味です。
風が吹けば桶屋が儲かる
一見関係ないことが連鎖して、予想外の人や事に影響を与えるという意味です。
腹八分目に医者いらず
過度に食べないことが健康の秘訣であるという意味です。
覆水盆に返らず
一度起きたことは取り返しのつかないという意味です。
捕らぬ狸の皮算用
まだ手に入っていないものの利益をあてにすることの愚かさを指摘します。
本末転倒
大事なこととそうでないことを取り違えることを意味します。
枚挙に暇がない
数え上げるほど多くの例があるという意味です。
味噌もくそも一緒
良いものも悪いものも区別なく同じように扱うことを意味します。
無い袖は振れぬ
持っていないものは提供できないという意味です。
無理が通れば道理引っ込む
力ずくで事を進めれば、正しい理が通らなくなるという意味です。
名は体を表す
名前はその人や物の性質を反映しているという意味です。
木に竹を接ぐ
自然に合わない無理な組み合わせをすることを意味します。
目から鱗が落ちる
あることをきっかけにして急に理解が深まることを意味します。
目くそ鼻くそを笑う / 目糞鼻糞を笑う
自分も他人も同じような欠点を持っているのに、他人の欠点を笑うことを意味します。
目には目を、歯には歯を
同じ方法で仕返しをするべきだという意味です。復讐の原則を示しています。
門前の小僧習わぬ経を読む
環境の影響で自然と知識や技能が身につくことを意味します。
柳に雪折れなし
柔軟なものは外部の圧力に対しても折れずに耐えられるという意味です。
油を売る
本来の仕事をせずに時間を無駄に過ごすことを意味します。
有言実行
言ったことを実行に移すことの大切さを表します。
与えられた馬には歯を見るな
贈り物の価値を吟味しないことのたとえです。贈り物に対する礼儀を示します。
用心棒に用はない
本当に必要とされる時には使われないという逆説的な意味を持ちます。準備はしておくものの、実際には使われることが少ないことを表します。
立つ鳥跡を濁さず
去る者は綺麗に後処理をして去るべきだという意味です。
立て板に水
話が非常に滑らかであることを意味します。
良薬は口に苦し
良い助言は聞きづらいものだが、それが最も役に立つという意味です。
最後に
この記事では、広く使われている140以上のことわざとその意味を一挙に紹介しました。
これらの言葉には、人生の指針となる深い洞察が込められています。
喜びや悲しみ、成功や挫折など、人生の様々な局面で私たちを導く力を持っています。
この記事を通じて、古くから伝わる知恵に触れ、日々の生活や決断に役立てるヒントを見つけていただければ幸いです。
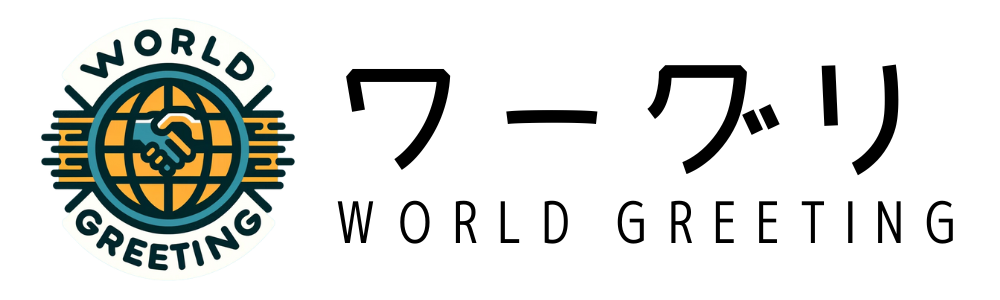
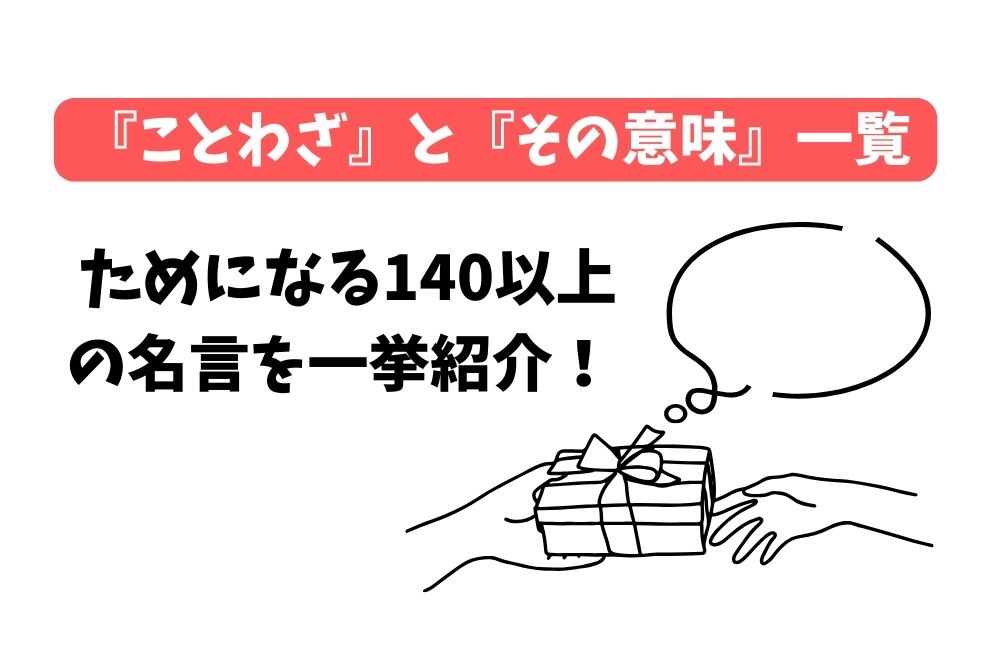

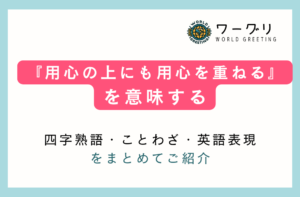
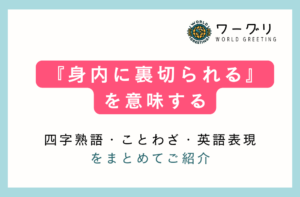
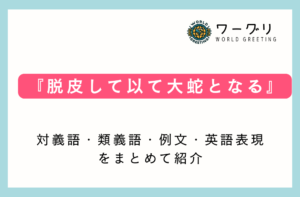
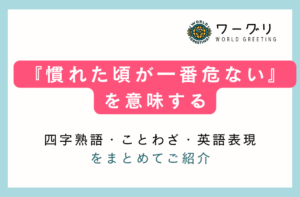
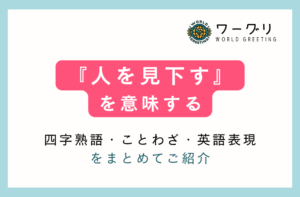
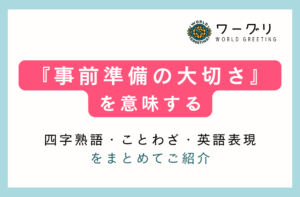
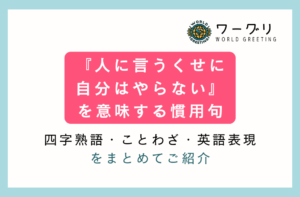
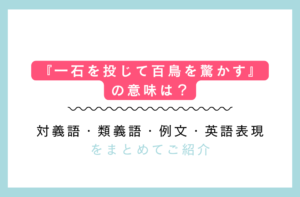
コメント